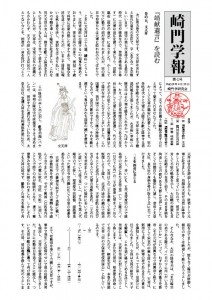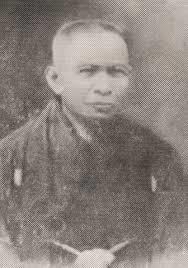北朝鮮の核武装が意味するもの
去る平成28年2月7日、北朝鮮が事実上の弾道ミサイルを発射した。このミサイルは射程1万から1万3千キロのICBM(大陸間弾頭ミサイル)であり、アメリカ本土を射程におさめる。すでに北朝鮮は2006年以来、これまで四回の核実験を行っており、金正恩は核弾頭の小型化にも成功したと主張している。よってそれが事実ならば、小型化した弾頭を弾道ミサイルに搭載すれば、アメリカ本土を核攻撃出来ることになる。
これは北朝鮮が、朝鮮有事に際するアメリカの介入を排除する抑止力を手に入れたことを意味し、戦後の米韓同盟にクサビを打ち込むものだ。というのも、朝鮮有事にアメリカが韓国を支援すれば、北朝鮮はアメリカ本土への核攻撃を示唆し、米韓同盟を無能化することが出来るからだ。この可能性が韓国側にもアメリカへの不信感を生じさせ、早くも韓国世論では核武装論が噴出しているという。
しかし同様の問題は、米韓のみならず北朝鮮の脅威を共有している我国とアメリカとの関係についても同様である。
MDは無用の長物だ
北朝鮮からのミサイル攻撃に対して、我が国は同盟国であるアメリカからMD(ミサイル防衛)を導入し配備している。MDは、敵国から発射された弾道ミサイルを、自国の迎撃ミサイルで撃ち落すシステムであり、我が国はアメリカに一兆円以上を払って、イージス艦など海上配備型の迎撃ミサイルであるSM3と地対空誘導弾パトリオットのPAC3を配備している。
しかし、実はこのMD、導入元のアメリカですら、これまでに行った迎撃実験は一度も成功しておらず、カネがかかる割りに実用性が乏しいシステムであることが指摘されている。アメリカは北朝鮮の脅威を喧伝し、自国の軍産複合体を儲けさせるために、法外に高く信頼性の低い兵器を我が国に売りつけているふしがある。
またMDが機能するためには、わが国政府はアメリカの軍事衛星から送られるミサイル発射情報に依存せざるを得ず、仮に北朝鮮がアメリカに対する核恫喝を行った場合は、前述した米韓同盟のように日米同盟も無力化されかねない。
揺らぐアメリカの信用
とはいっても、北朝鮮の核・ミサイル実験はもはや年中行事と化しおり、たしかに脅威ではあるが、所詮は周辺国から外交的な譲歩を引き出し、経済援助を手に入れるための空脅しに過ぎないという見方もあるだろう。
しかし、北朝鮮の後ろ盾となっている中国の脅威ははるかに現実的だ。周知のように、中国は近年における経済成長の鈍化にもかかわらず、軍事費は相変わらずの二桁増を続け、積極的な海洋進出を進めている。こうした軍事的拡張の結果、仮に中国が尖閣諸島に侵攻しわが国と交戦状態に突入した場合、我が国がアメリカから導入したF15戦闘機やオスプレイによって迅速に対応し、尖閣を死守ないしは奪還することが出来たとしても、中国は軍事行動のレベルをエスカレートして我が国に核恫喝を仕掛ける可能性がある。
また日米安保に基づいて日本を援護するアメリカに対しても、在日米軍ないしはアメリカ本土への核攻撃を示唆して中国が核恫喝を行えば、アメリカは対日防衛を躊躇し、我が国民が期待するアメリカの核の傘は機能せず、核戦力を持たない我が国は中国への軍事的屈服を強いられる他ない。それでなくても近年、中東政策に膨大なコストを浪費し、財政的な制約を抱えるアメリカは嫌が応にも孤立主義的な性格を強め、中国の台頭を抑止する意思も能力もない。つまり日米同盟論者が信仰するアメリカによる核の傘は破れる以前に被さってもいないのである。
我が国も核武装を検討していた
こうしてアメリカの核抑止力に対する信頼性が揺らぐ中、我が国が上述した中朝の脅威に対抗し、自主的な核抑止力を保持することで北東アジアにおける力の均衡を維持しようという意見が出てきても不思議ではない。
事実過去にも、1964年に中国が核保有を宣言した際には、時の佐藤栄作内閣が我が国の核武装に向けて動き出し、同じく佐藤政権下の68年から70年までの間に、日本が自力で核武装できるかの調査が行われた。その結果、内閣調査室から提出された報告書によれば、我が国が原爆を少数製造することは当時のレベルでもすでに可能であり、比較的容易であると指摘されている。具体的には、黒鉛減速炉である東海炉(98年運転終了)は兵器級プルトニウム生産に適しており、プルトニウム原爆であれば200から300発製造可能」と記されている。
その後、周知のように、佐藤政権は67年に非核三原則を打ち出し、72年には沖縄返還が実現したが、その裏には有事の際にアメリカが沖縄に核兵器を持ち込むという密約があった。佐藤はアメリカの説得に屈し、アメリカの核に期待して我が国の核武装を断念したのである。
原爆製造は技術的に可能だ
周知の様に原爆には、プルトニウム型とウラン型がある。我が国が広島に落とされたのはウラン型で長崎はプルトニウム型だ。
まず、プルトニウム型に関して、すでに我が国は、原発の使用済み核燃料から回収した余剰プルトニウムを50トン近く保有している。このプルトニウムで原爆を製造するためには、プルトニウム239 の比率を93%以上に高めて兵器級プルトニウムを精製せねばない。そしてその作業は、核燃料サイクルと呼ばれる、高速増殖炉を使った核燃料の再処理によって可能であるとされるが、この核燃料サイクルは、複雑な構造から運用が上手くいかず、福島県敦賀市にある高速増殖炉もんじゅも実用化の目処が立っていない。
そこで、次にウラン型であるが、これは青森県六ケ所村にあるウラン濃縮施設でにおいて、天然ウランから核分裂を起こしやすいウラン235を抽出することによって製造が可能である。
現行法でも核武装は可能だ
この様に、佐藤内閣時の報告書が答申した様に、我が国の原爆製造は技術的には可能であるが、核燃料サイクルが実現しない限り、資源小国である我が国は天然ウランの輸入に頼らざるを得ない。また、上述した我が国の核再処理施設や核濃縮施設にはIAEAの査察官が常駐しているため、我が国が原爆製造に着手するためには、NPTから脱退せねばならない。しかし、NPTは第10条で「 各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。」と明記されているのであり、前述した最近の情勢変化を受けて、我が国が「自国の至高な利益」を守るためにNPTを脱退することは、国際法で認められた正当な権利である。
また、国内法的にも、現行の原子力基本法には、我が国の核開発について、「確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行う」と記されており、我が国の「安全保障に資する」核開発としての核武装を禁ずるものではない。
さらに、憲法とのかねあいでも、1957年、岸信介首相(当時)は、現行憲法のもとで許される自衛権の行使の範囲内であれば、「自衛のためなら核兵器を持つことは憲法が禁じない」との見解を述べている。これは、我が国の核武装が、憲法が行使を認める個別的自衛権の範疇だということである。
このように、我が国の核武装は、憲法改正を必要とせず、現行法の枠内で実現可能だ。これは日米の一体的運用を前提にしたMDが集団的自衛権の行使にあたり、憲法違反の疑いがあるのに比べて余程政治的なハードルは低い。要は、安倍首相の政治決断次第だということなのである。
米国主導の核秩序から脱却せよ
とはいえ、アメリカは、戦後アイゼンハワーが行った「アトムズ・フォー・ピース」演説以来、核の平和利用と引き換えに核燃料や原子力技術を西側に輸出する政策を堅持しており、我が国がNPTを脱退し、原子力の軍事転用の意思を表明すれば、日本への核燃料の輸出を停止する可能性がある。とくに我が国が天然ウランの過半を輸入しているオーストラリアとカナダは共にアングロサクソン諸国であるから、アメリカに同調する可能性が高い。
したがって、今後我が国がNPT体制のようなアメリカ主導の核秩序から離脱する場合には、ウラン等の供給ルートを多角化することによって重要資源の安定調達を確保する必要がある。その際、新たな供給源になりうるのは、アメリカ主導の核秩序と一線を画するロシアやインドである。ロシアは国内にウラン鉱山を有するのみならず、世界のウラン生産の27%を占めるカザフスタンのウラン開発を主導している。またインドはNPTの非加盟国でありながら、我が国と原子力協定を結んでおり、核開発での協力が期待できる。
重要なのは、両国が中国と長大な国境線で接し、安全保障上の脅威を我が国と共有していることだ。ロシアは中国と沿海州の領有やシベリアへの越境移民などの問題をめぐる潜在的な対立を抱え、またインドもアクサイチンやラダックなどで中国との領土紛争を抱え、中共軍による越境侵略が後を絶たない。周知のように、我が国はロシアと北方領土問題を抱え、日露平和条約交渉は中断されたままであるが、両国の和解を妨害しているのはアメリカである。過去にも、ダレスの恫喝で日露交渉は頓挫し、現在もアメリカは安倍首相の訪露に反対しているという。
安倍首相は、アメリカを過剰に怖れ、対米譲歩を繰り返しているが、かつて98年にBJP(インド人民党)政権下で核実験を行ったインドは、いまもアメリカとの友好関係を維持しているし、現首相のナレンドラ・モディー首相も一時は、アメリカから過激なヒンドゥ・ナショナリストとしてビザの発給を停止されていたが、首相に就任した14年には訪米してオバマ大統領と「民生用原子炉協定」について協議している。同様に、我が国の核武装も、アメリカからの自立ではあっても、訣別を意味する訳ではない。既成事実を積み重ね、「日米同盟」を漸次相対化していくプロセスが必要だ。
核武装は経済政策としても有効
我が国が核武装するに際して、その抑止力を最大限に発揮できるのは原子力潜水艦である。原潜は、通常動力の潜水艦より静粛性には劣るが、潜航時間が長く、秘匿性・生残性に優れている。よって、これに核弾頭を装備したSLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)を搭載すれば、敵からの核攻撃に対する第二撃(報復)能力を確保し、さかのぼって敵に第一撃を思いとどまらせることが出来る。
その際、我が国が保有する原潜はあくまで国産での開発をめざすべきだ。前述したように、現在の自衛隊が装備している、F15戦闘機、イージス艦、パトリオットミサイル、オスプレイなどの兵器は、アメリカの継続的な技術支援、作戦面での協力がなければ運用不可能であり、それが我が国の自立を妨げる重大な要因になっている。よって我が国政府は、兵器の国産化を推進することによって、軍事産業における技術革新を促し、アメリカへの軍事依存を漸次軽減して行かねばならない。
また原潜を始めとする兵器の国産化は、政府主導の産業政策、ケインズ的な有効需要政策としても有効である。ある試算によると、戦略ミサイル原子力潜水艦を一隻保有するためにかかる経費は、9360億円であり、その開発期間が各5年として4隻保有した場合に要する20年でかかる経費の総額だけでも7.5兆円になるという。よってこれらの事業に対する政府支出がもたらす経済的な波及効果は計り知れず、かねてよりデフレ不況からの脱却を目指す我が国にとって、景気浮揚策としても有効であると思われる。
核武装なき対米自立は幻想に過ぎない
これまで縷々述べたが、つまるところ、国家の防衛政策は「我が国以外は全て仮想敵国」(チャーチル)だという原点から出発せねばならない。中朝の脅威のために「日米同盟」に頼る考えも、また対米自立のためにアジアとの「友愛」に期待する考えも、共に我が国を守ることは出来ない。我が国を守りうるものは、唯一我が国のみである。このことを自覚すれば、我が国が生き残る道は、唯一核武装による国家の自主独立しかないと確信する。
 この度、小生等が主宰する大アジア研究会の機関紙として『大亜細亜』を創刊する運びとなった。大アジア研究会は、戦前における大アジア主義の思想と運動の研究とその現代における実践を目的とした有志の勉強会である。本紙『大亜細亜』は、季刊での発行を目指し、日ごろの研究と実践の成果、今後の方針などを発表して参りたい。(←ダウンロードは画像をクリック)
この度、小生等が主宰する大アジア研究会の機関紙として『大亜細亜』を創刊する運びとなった。大アジア研究会は、戦前における大アジア主義の思想と運動の研究とその現代における実践を目的とした有志の勉強会である。本紙『大亜細亜』は、季刊での発行を目指し、日ごろの研究と実践の成果、今後の方針などを発表して参りたい。(←ダウンロードは画像をクリック)