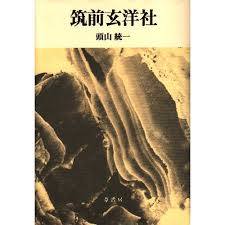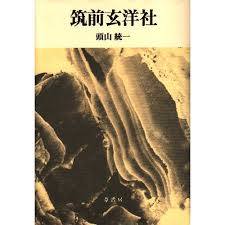 ①はじめに
①はじめに
最近、小林よしのり氏が『大東亜論』を出したせいか、世上における大アジア主義への関心が高まっているようです。この『大東亜論』の感想はさておき(小生はすこぶる興味深く拝読しました)、同書の思想的素地を成していると思われる文献が、頭山統一先生の『筑前玄洋社』(葦書房)であります。
統一先生は、頭山興助先生のお兄様であり、本書、『筑前玄洋社』は、頭山満翁を中心とした我が国の大アジア主義の思想と運動を理解する上での必読文献と申しても過言ではなかろうかと思います。
そこで、以下では本書を読み解くことによって、大アジア主義とは一体なんであったか、そしてそれが現代を生きる我々にとっていかなる意味を持つのかについて、今一度考察して参りたいと思います。
②玄洋社三則の意味
まず本書は冒頭から維新史の核心を衝いています。いわく幕末・明治を通じて我が国民の共通意識であったのは、「尊王・攘夷・公議公論の三位一体をなす論理であった」と。
幕末に佐幕か討幕かの争いがあり、明治になっても政府・吏党と在野・民党の争いがありましたが、両サイドを通じて尊皇という一点にはいささかの相違もありませんでした。まずこれが今日の民主主義とは根本的に異なる点です。
次に攘夷ですが、これは明治国家における国権の主張となり、公議公論は民権の主張となります。もっとも、両者はむしろ尊皇という不動の前提を支える二本の柱、あるいは別の言い方をすれば、尊皇という精神を発揚せしめる双翼であります。
と申しますのも、ご皇室の尊厳を護持するために、国家の内外に対する強固な権力基盤が必要であることは論を待ちませんが、一方で国民は等しく天皇陛下の大御宝なのでありますから、その国民の富貴は、すなわち陛下の富貴であり、国民が自由に意見を述べることは、明治陛下が五箇条の御誓文に於いて国民に恩賜なされた神聖な権利であります。
よって、いくら国権を確立する必要があるといっても、そのために大御宝である国民の権利が抑圧され、その生活が窮迫することは、もとより聖旨にもとり、ひいてはご皇室の尊厳を損なうことにもなります。
このように、当時の国民精神としては、尊皇という理念を媒介して、攘夷としての国権主義と公議公論としての民権主義が渾然一体のごとく結合している、ここに顕著な特徴があるのでありまして、在野の民権団体と出発した玄洋社もその例外ではありませんでした。
だからこそ、彼らはその有名な憲則の第一条に「皇室を敬戴すべし」、第二条に「本国を愛重すべし」と掲げながら、第三条に「人民の権利を固守すべし」と説いて、尊皇を前提した国権と民権の調和を志向しているのであります。
③我が国において、民権と国権が一体であることを物語る事例として、筆者は明治十年の西南の役で、西郷軍が必ずしも賊軍とは言い難い事実を指摘しております。どういうことか、以下に本文を引用いたしましょう。少し長いですが、ご容赦下さい。
「ここで明治六年の征韓論決裂から、十年の西南の役までの時期を、歴史の距離感を正確に調整して眺めるなら、帰郷したとはいえ、薩摩の西郷は陸軍大将の官職を奪われたわけではなく、まだただの無位無官の「在野」の人ではない。とすれば大久保が代表する東京政府と西郷の対立をいわゆる「朝野の対立」とする表現は実は正確でなく、正しく具体的に言えば、「東京の大久保体制と、薩摩の西郷体制が対決する明治政権内部の抗争」なのである。現代の眼で眺めればどうでもよいことのようであるが、実はそうではない。「東京の大久保体制」を攻撃し倒そうとたんに主張するだけでなく現実に画策する西南有志にとって、西郷が、たんに在野の雄ではなく、日本で唯一の「元帥陸軍大将」であることは、実に大切な条件であり名分なのである。」
なるほど西南の役は、国家の内戦でありますが、それは西欧やシナの様に国王率いる政府軍と人民代表を自称する反乱軍の戦いではありません。むしろ両者は尊皇の大義を掲げ、何方がより臣下としての正統に相応しいかという争いをしているに過ぎないのであります。
④(補足)玄洋社の民権思想について
先の繰り返しになりますが、玄洋社の民権思想は、現行憲法が依拠するデモクラシーの思想とは全く似て非なるものです。それは玄洋社の前身で、箱田六輔を社長、頭山満を監事に配した向陽社の民権思想に関する本書の以下の記述からも明らかです。
いわく「向陽社の普選思想は、まったく日本的な君民一体の国体観の常識から出たものだった。無私にして、民の幸福を皇祖に祈られることをみずからの務めと信じられる祭祀権者天皇は、人民を「おおみたから(公民)」として、その権利を保証して、慈しまれる。権利を保証せられた人民(臣民)は、天皇に捧げる忠誠心において万民貴賎のへだてなく平等である。大臣も乞食も、天皇に対して完全に平等に忠誠を尽くそうとする、誇らしき義務意識を有する。この日本的「臣民の権利義務」は、西欧における君主あるいは国家が、人民に対し、その安全を保証するサーヴィスを提供し、人民はそのサーヴィスに相応する代価を、君主、国家に支払うという対立的契約観念が源流となる「権利・義務」概念とまったく異なるものであることは明瞭である」。
さらに、こうした彼らの民権思想は、上述した向陽社の主導で設立された福岡全県の民権組織である筑前共愛会が明治13年、元老院に提出した「筑前共愛会憲法私案」において、参政権の資格として「土地保有・財産・納税額による制限を一切うたわず、ただ一家の戸主たることのみを条件としている」ことにも顕著に現れています。我が国の国民が、ご皇室を宗家に仰ぐ一戸の家族であることを思えば、確かに民権の主体は個人であるよりも、家族、特にその首長である家長であるべきだという彼らの主張は頷けます。
⑤頭山翁、玄洋社は変節したのか。
後に明治24年の第二回総選挙に際して、頭山翁はときの松方正義内閣、なかでも内相の品川弥二郎と結託し、政府による選挙干渉、民権派の弾圧に加担したことから、これを頭山翁の変節、玄洋社が民権団体の看板を捨てて国権主義に転向した契機と見なす意見がありますが、それは間違いで、むしろ変節し転向したのは翁を取り巻く、政府であり民党の方です。
と言いますのも、政府の方では万機公論に決すべき大政を薩長藩閥が壟断し、明治15年の集会条例改正、明治16年の新聞紙条例改正、出版条例改正と続く一連の言論弾圧政策によって民党を圧迫する一方で、不平等条約の改正交渉に於いては西欧列強に対して屈辱的な譲歩を繰り返し、国民の怒りを買いました。
しかし民党の側ではどうかというと、それまで条約改正(国権)と国会開設(民権)を不可分のテーマとしてきた板垣退助率いる愛国社の運動が、政府に対する戦略的妥協によって条約改正の要求を引っ込め、国会開設期成同盟への改組の後は、その運動目標を国会開設に限定したように、国権の主張を放棄して民権の主張に偏向し出したのです。愛国社は板垣退助率いる土佐の立志社が中心になって結成された民権派の全国組織であり、大久保暗殺後の明治11年に開かれた愛国者再興集会には、福岡を代表して後に玄洋社社長を務める進藤喜平太と頭山満が参加しています。その後、福岡と愛国社の繋ぎ役は、共愛会を代表して箱田六輔が担い、彼は板垣をして「箱田あれば西南方面は安心なり」とまで評さしめましたが、頭山翁は、次第に上述した民党の変節と堕落に幻滅し、むしろ一部では「国権等党」と揶揄されていた熊本紫溟会の佐々友房等と交流するようになりました。